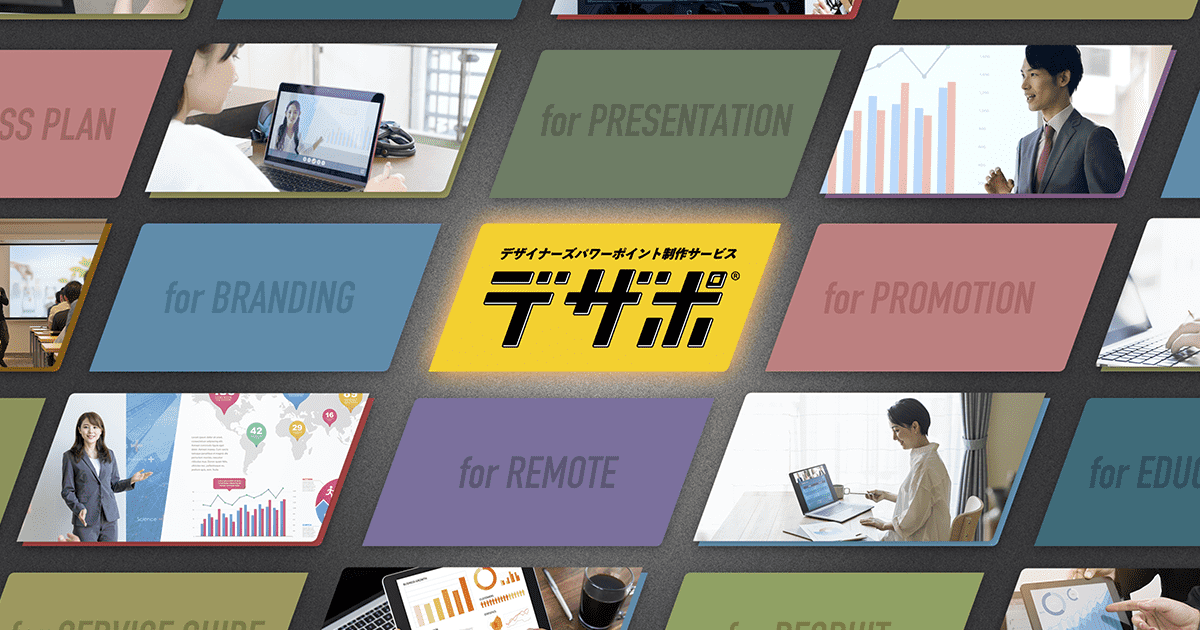説得力のある企画書を作るのは、簡単なことではありません。「企画書と提案書の違いが分からない」「何から書けばいいのだろう」と頭を抱えるビジネスパーソンも多いことでしょう。
今回の記事では、説得力のある企画書を作成するためのノウハウを集めました。企画書の基礎知識から基本構造、具体例やデザインのコツまで解説しています。企画書の作成にお悩みの方は、ぜひお読みください。
企画書の作り方1:基礎知識
新しいプロジェクトを立ち上げる際、企画書の提出を求められるケースは少なくありません。発案者はアイデアを実現するために、説得力のある企画書を書く必要があります。
本項では「企画書」の基本的な定義と、混同されがちな「提案書」との違いについて解説します。
企画書とは
企画書とは、新商品や新規プロジェクトなどを実行する前に作成する資料です。企画書は主に、関係者の承認と理解を得たり、予算や人員などの社内リソースを確保したりする目的で作成されます。
そのため企画書を作る際は、内容や目的、スケジュール、収益性などを詳細に記載します。関係者の納得と賛同が得られるよう、実務レベルまで落とし込んだ記載が必要です。
企画書と提案書の違い
企画書と提案書は、どちらも新しいことを始めるために作成します。しかし、目的や内容には以下のような違いがあります。
| 対象 | 目的 | 内容 | |
|---|---|---|---|
| 企画書 | 社内 | 新しい企画の実現 | 具体的な行動計画 |
| 提案書 | 社外、顧客 | 大まかな方向性を示す | 企画の方向性 |
企画書の作り方2:基本構造
企画書は、主に次の5つを基本構造として作成します。本項では、各項目について1つずつ解説していきます。
- 現状分析:どうなっているか
- 目的とゴール:何のために
- 内容:誰に、何を、どうやって
- スケジュール:いつからいつまで
- 収益性:いくらなのか
1. 現状分析:どうなっているか
企画書を作成するには、初めに現状分析を行い、「現状がどうなっていて何が課題なのか」をまとめます。社内はもちろん、社外の状況も含めて分析しましょう。例を挙げると、下記のような項目があります。
- 内部環境:売上高の増減、社内リソースの状況など
- 外部環境:競合他社の商品開発、業界の動向など
現状分析は重要な部分であり、この良し悪しで説得力が左右されます。分析内容をロジカルに伝えるために、参考文献や統計資料を用いるのもおすすめです。
2. 目的とゴール:何のために
現状分析で課題を浮き彫りにできたら、その目的(解決手段)と、ゴール(どのような状態)を目指すのかを明確に示します。以下はその一例です。
- どの課題に対してアクションするのか
- 課題解決のために何が必要なのか
- 企画を実行すると、どのようなメリットが得られるのか
目的とゴールを言語化することで、関係者の認識違いを防ぐと同時に、企画の軸と方向性を定められます。
3. 内容:誰に、何を、どうやって
目的とゴールが決まったら、次は企画の内容を記載します。軸となるのは以下の3点です。
| 誰に | ターゲット層(ペルソナ)の設定 |
| 何を | サービス、製品、イベントなど企画内容の詳細 |
| どうやって | 提供方法、使用ツール、宣伝方法など具体的な手段 |
企画内容はテキストだけでなく、数値やグラフなどを用いると、より明確に伝わります。関係者が納得できるよう、具体的なところまで落とし込むのが大切です。
4. スケジュール:いつからいつまで
企画書にはっきりとした期限を記載すると、具体性がより向上します。社内リソースの不足やトラブルが発生する可能性を考慮し、余裕のあるスケジュールを組むのが肝心です。イベントなどの予定も忘れずに織りこみます。
またスタートとゴールの間には、ミーティングや仮設定完了など「マイルストーン」の設定をおすすめします。企画実行時にマイルストーンが定まっていると、スケジュール管理がしやすくなるためです。
5. 収益性:いくらなのか
最後に、収益性についてまとめます。関係者の理解と承認を得るためには、以下のポイントをしっかり押さえて、メリットを伝えなければなりません。
- 企画の実施によって得られる収入とその時期
- 必要な投資額
- 費用対効果の金額
なお、企画書の説得力を高めるために、収支の金額はできるだけ具体的に記載しましょう。
企画書の作り方3:フレームワーク

フレームワークとは、現状分析や企画立案になどに使われるロジカルな思考方法です。説得力のある企画書を作るには、フレームワークの活用が効果的です。
本項では、企画書に役立つフレームワークとして、下記の4種類を解説します。
- 6W2H
- 4C分析
- SWOT分析
- STP分析
1. 6W2H
6W2Hとは、情報の整理に効果的なフレームワークです。以下の流れに沿って、質問に答えるように内容を整理していきます。
| 6W2H | 意味 | 内容 |
|---|---|---|
| Why | なぜ | どうして企画を実施するのか |
| What | 何を | 何を実現したいのか |
| Where | どこに | どの市場に参入したいのか |
| Whom | 誰に | 誰をターゲットにしているのか |
| When | いつ | いつからいつまでかかるのか |
| Who | 誰が | 誰が担当者・責任者になるのか |
| How | どのように | 具体的な実現方法は何か |
| How much | いくらで | 収入額、投資額、費用対効果はどれくらいか |
6W2Hはビジネス書や報告書にも使用される、使いやすいフレームワークです。
2. 4C分析
4C分析は、現状分析をするためのフレームワークです。主に以下の項目について、情報収集をしていきます。
| 4C | 意味 | 内容 |
|---|---|---|
| Customer | 市場・顧客 | 業界の規模、顧客のニーズなど |
| Competitor | 競合 | 競合他社のシェアと特徴、新規参入の脅威など |
| Company | 自社 | 企業理念、事業の現状など |
| Channel | 流通チャネル | 販売ルート、流通経路など |
※流通チャネルを除いた「3C分析」も使われている
3. SWOT分析
SWOT分析は、自社の内外を取り巻く環境を分析するためのフレームワークです。4C分析で収集した情報に基づいて、内部環境・外部環境を分析します。
| SWOT | 環境 | 意味 | 内容 |
|---|---|---|---|
| Strength | 内部環境 | 強み | 自社の強み、競合他社に対する優位点など |
| Weakness | 内部環境 | 弱み | 自社の弱点、不足している社内リソースなど |
| Opportunity | 外部環境 | 機会 | 景気変動や法改正、流行などのビジネスチャンス |
| Threat | 外部環境 | 脅威 | 競合他社の動き、市場の停滞などのマイナス要因 |
SWOT分析で重要なのは「何のために分析するか」です。それにより視点が変わるので、企画の目的を明確にしてから分析を始めましょう。
4. STP分析
STP分析は市場を細分化し、ターゲット層に提供する価値を決めるためのフレームワークです。
| STP | 意味 | 内容 |
|---|---|---|
| Segmentation | 細分化 | 市場を地域や性別、年齢、価値観や行動パターンなどで分類 |
| Targeting | ターゲット | ターゲットとなる市場を定める |
| Positioning | 立ち位置 | 自社製品の機能・価格帯などの立ち位置を決める |
STP分析は、必ずしもこの順番で分析する必要はありません。順番を前後することで、より効果的なマーケティング戦略を見いだせる場合もあります。
企画書の作り方4:記載例とポイント
企画書の構成を決める際は、意図がしっかりと伝わるように工夫しましょう。6W2HやSWOT分析などの手法で整理した情報を、分かりやすく記載していきます。
企画書は文章だけでなく、図解やグラフも取り入れるとより良いです。本項では、実際の企画書の記載例と、ポイントを解説します。
実際の記載例
企画書の基本構造を各ページに落とし込んだ一例です。
| ページ | 内容 | 詳細 |
|---|---|---|
| 1枚目: 表紙 | タイトル | 企画のタイトル(プロジェクト名) |
| 作成日、作成者 | 日付、作成者名(担当者、担当部署など) | |
| 2枚目: 現状分析 | 現状の課題・企画の動機 | 現状分析で浮かび上がった課題 ※課題が複数ある場合「背景1」「背景2」などと分けて記載する |
| 3枚目: 目的・内容 | 課題解決の方法 | 現状の課題に対する解決方法 ※複数ある場合は「ポイント1」「ポイント2」などと分けて記載し、解決できる理由も添える |
| 4枚目: ゴール | 効果の見込み | 現状と企画終了後を比較して、どのような効果が見込まれるのかを記載する。効果の理由やパーセンテージなどの数字を具体的に示す |
| 5枚目: 収益性 | 企画の収益性 | 収入額、投資額、費用対効果 |
| 6枚目: スケジュール | 企画の日程 | 企画開始から、ミーティングや仮設定完了などのマイルストーン、完了までのスケジュール |
企画書に内容を裏付けるためのデータや資料を添付すると、より具体的なイメージを持ってもらえます。
書き方のポイント
説得力のある企画書を作るには、書き方にもコツがあります。
作成を始める前に「何枚目に何を盛り込むか」を決めておくのが、スムーズに作成するコツです。まずはページごとに下書きをして、論理の破たんや情報の漏れがないかどうかを確認します。なお、下書きは箇条書きでも構いません。
売上高や経費の削減額、利益率などの情報は、具体的な数値を記載しましょう。企画書の説得力がぐっと向上します。
企画書の作り方5:デザインのコツ

企画書の内容をしっかりと伝えるには、デザインも重要です。無造作に文字を並べただけの企画書は、読み飛ばされてしまう可能性があります。
本項では、企画書作成にパワーポイントを用いることを前提として、デザインのコツを4つ解説します。
- 1枚のスライドにつき1つの情報を載せる
- フォントにこだわる
- 配色のポイント
- レイアウトのコツ
1. 訴えたいことは1スライドにつき1つに絞る
1枚のスライドに訴求したいことが複数あると、メッセージが伝わりにくくなったり、主旨が埋もれたりしがちです。また、情報を詰め込むことで必然的にスライドの余白が減るので、見る人に窮屈な印象を与えるかもしれません。
これを防ぐには「訴えたいことは1スライドにつき1つに絞る」ことを心掛けましょう。情報を詰め込んだ場合に比べて、スライドの内容が格段に分かりやすくなります。
2. フォントにこだわる
読みやすい企画書を作成するには、フォント選びも重要です。まったく同じことを書いたテキストでも、フォントが適切かどうかで、伝わりやすさが変わってしまいます。
企画書に適したフォントには、以下の特徴があります。
- 一般的で見慣れたフォント
- 視認性(見やすさ)に優れている
- 太字に対応している
企画書をパワーポイントで作成する場合はWindows版なら「メイリオ」「游ゴシック」「BIZ UDPゴシック」、Mac版なら「ヒラギノ角ゴ」などがおすすめです。視認性が高い他、太字にも対応しているため、重要箇所を強調したい際も便利です。
3. 配色のポイント
企画書をカラーで作成する際は、色を使いすぎないように気を付けましょう。一般的に、文字色を含めて3色に絞ると、情報の重要度が分かりやすくなると言われています。
| 色の役割 | 選択基準 |
|---|---|
| 文字(ベースカラー) | 文字には黒または濃いグレー、背景には白系統など |
| メインカラー | ・コーポレートカラー ・強調したい箇所に使う |
| アクセントカラー | ・メインカラーの反対色など ・注目してほしい箇所に使う |
色を増やしたい場合は、3色の明度や彩度(色の鮮やかさ)を変えると、バリエーションが広がります。
4. レイアウトのコツ
前述した通り、余白がないスライドは窮屈な印象を与えてしまいます。スライドの周囲はもちろん、文章の行間や文字間にも、ある程度の隙間が必要です。文字がぎっしり詰まったり、逆に離れすぎて閑散としたりしないよう、適切な間隔を意識しましょう。
グラフや図表などのオブジェクトは、大きさや間隔を統一し、まっすぐに配置すると見やすくなります。画像と説明文など、関連性のあるオブジェクトは近くにまとめて、一体感を持たせるのが基本です。
【まとめ】企画書作りが負担になるときはプロに依頼しよう

説得力のある企画書を作るには、内容を充実させるのと同時に、デザインの細部にも配慮しなければなりません。しかし、繁忙期や業務が立て込んでいるときなどは、企画書作りに十分な時間を割けない場合もあるでしょう。
そのようなときは、企画書の作成を外部に依頼するのも1つの方法です。プロによるレベルの高い企画書を作れるだけでなく、資料作成業務の負担を削減し、コア業務に注力できるというメリットも得られます。
株式会社ユニモトが提供する「デザポ」は、オーダーメイドのパワーポイント資料を制作するサービスです。経験豊富なグラフィックデザイナーが「デザインの力」を用いて、プロジェクトのポテンシャルを最大限に引き出した企画書を作成します。
デザポの公式Webサイトには、経験豊富なプロのデザイナーが作成した実例を数多く掲載しています。パワーポイント資料の作成を外部に依頼したいとお考えの方は、ぜひご覧ください。